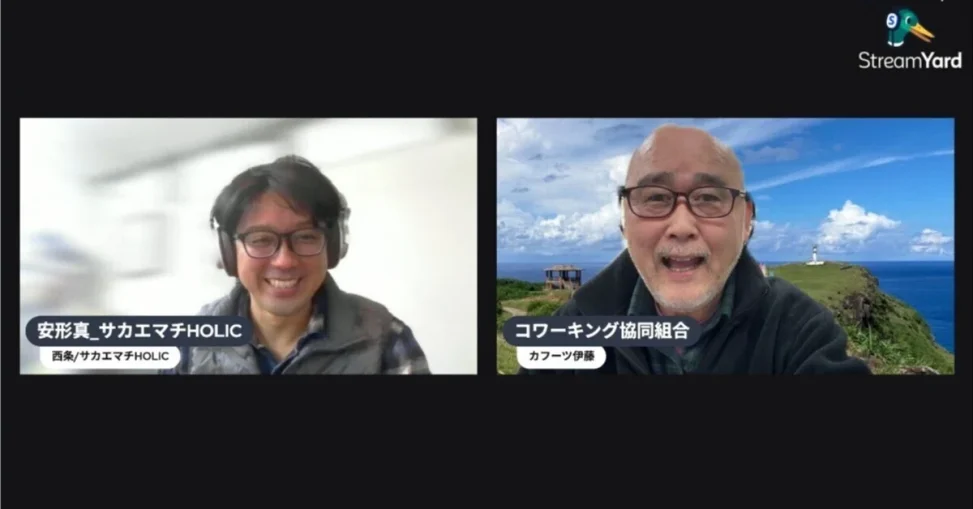〜トーキング・コワーキングVOL.8〜
(Text & 写真:伊藤富雄)
※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年2月15日の記事を一部編集して転載しています。
*****
昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.8」は、愛媛県西条市の「サカエマチHOLIC」の安形 真さんをゲストにお迎えして配信した。安形さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。
配信後、そのままYouTubeで一般公開しているので、ぜひ、こちらでご覧ください。
安形さんは異色の経歴の持ち主だ。冒頭に自己紹介されているが、もともと愛知県の出身で、なんと一時期、探偵をしていた、と。そうそう、素行調査とかの探偵。まあ、滅多にお目にかかることはないと思うけれど、お目にかかってしまった。
その後、会計事務所に勤務の後、農業に関わるようになり、農業レストランも経営されていたが、身体を壊した後、起業支援の職につくようになる。この一連の経験が、後々のコワーキングにつながってくる。
場所を愛媛県西条市に移し、地域おこし協力隊員としてカツドウをはじめた際に、ここでも起業支援ができればいいと考え、コワーキングスペースを開業する。←この行動力を見習いたい。
ぼくは地域おこし協力隊こそが、そのカツドウの拠点としてローカルコワーキングをやればいいのにとずっと思ってるのだが(その講座も企画したことがある)、それを安形さんはすでにやっておられた。
西条ではじめた起業相談では起業家マインドの醸成から、経営戦略、マーケティング、販路開拓、メンタルマネジメント、バックオフィスに至るまで幅広く対応していて、相談件数は年間100件を下らないという。スゴイ。
ちなみにこれは、2021〜22年の起業支援活動の報告書。
ところが、その起業支援は、地元自治体からの受託による仕事だったのだが、この配信の前日に、「無料相談は今年度で終了することになった」とFacebookに投稿してこられたのを見てオドロイタ。どゆこと?
どうやら、(たぶん国からの交付金の関係かと思うが)役所のほうの予算が確保できなかったらしく、やむなく終了となったらしい。と、この配信中に事情を説明されたのだが、この話には続きがある。
そのFacebookの投稿を見られた多くの方々から、「やめないで」「続けてほしい」「ついてはこういう案件があるのだが」と、続々と支援依頼が舞い込んできたらしい。安形さんにとっては思いもしない展開。いい話ですよね。
それもきっと、これまでの安形さんのカツドウぶりを見て信頼を得ていたからに相違ない。人って、ちゃんと見ているのだ。
で、この起業相談に「移住」が絡んでくる。中には、自分のやりたい事業に使える不動産物件があれば移住してくる、という人も現れる。そこで考案されたのが「事業用空き家バンク」だ。
通常、「空き家バンク」に登録される物件は、居住用であるのが前提だが、西条市では事業に供される目的の物件も空き家バンクに登録、公開されている。それを自治体に働きかけたのも安形さんだ。
このページには、物件の一覧と、希望に叶う物件があれば借りたい、もしくは買いたいという起業家の人たちが掲示されている。言ってみればマッチングだが、こうして見える化するところがオモシロイ。こういう取り組みは、ほかの地方でもやってみたらどうか、と思う。

ちなみに、この取り組みはあくまで起業支援の一環であって、不動産取引の仲介業ではないので、一切手数料を徴収していない。頭が下がる。
そして、こうしてまちのためにさまざまなカツドウをしていくうちに、たくさんの仲間ができ、多くの賛同を得て設立したのがコミュニティ財団の「えひめ西条つながり基金」だ。

「え?財団?」、そう、ぼくも最初聞いたときには耳を疑った。しかし、401名の市民から428万円余りの寄付を集めて、本当に財団を設立したのだ。
また、なんで?と思うだろうが、動画でもお話いただいているが、コミュニティ財団は市民のお困りごとをみんなで解決しよう、というのがその趣旨。
つまり身の回りの困ってる人たちを助けてもいいよという「仲間」がいる、コミュニティがあるというのが前提で、ただお金を出すだけでなく、みんなで助け合って解決していこう、といういわばひとつの「運動」だ、と安形さんは言う。なるほど、「運動」ね。
ここに、財団が助成しているプログラムの一覧がある。いずれも、10〜20万円と比較的少額だが、確かに地元民にとっては困りごとばかりだ。
このイベントのゴミ問題なんか、地方都市あるあるの課題ではないかしらね。

財団法人を作った、そのことよりも、それを使って「運動」(=カツドウ)することのほうが大事。←ここ、コワーキングスペースを作ることよりも、「コワーキング」することのほうが大事、という話に似ている。
で、なんと、このコミュニティ財団が、その後、一年ほどで公益財団法人に認定された、というからオドロク。
この「コワーキングとコミュニティ財団」という組み合わせは、特にローカルのコワーキングにとっては有効に働くだろうと思う。
ただ、席を一日いくら、一ヶ月いくらで貸すだけではなく、そこを拠点とするカツドウの資金を集め、かつ提供する仕組みを自ら持ち、まちづくりに貢献するというアイデアは、ローカルコワーキングの果たす役割を示している。そして、それがあるがためにメンバーも集まり、カツドウ領域も広がる可能性があるので、ぜひ検討すべきだと思う。
ところで、最後の「安形さんにとってコワーキングとは一言で言って何ですか?」という質問には、こう答えられた。
コワーキングとは「家族」みたいなもの。
みんな、愛おしい。
結局、居場所なんですよ、うちらのコワーキングというのは。
だから、ふと帰ってきたら「おかえり」が言えると、いいっすよ。
この言葉にはジーンと来た。ほんと、そうです。ぼくらは「むっつり作業する場」を作って運営しているのではない。「おかえりと言ってあげられる居場所」だ。それがつまり、コワーキングをベースとするコミュニティ。
そんな話以外にも、コワーキングを運営していく上で大変参考になるインサイトがいろいろ共有されているので、ぜひ、YouTubeでご覧いただきたい。